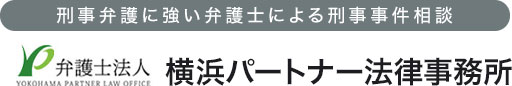学校関係者による大量盗撮画像“提供”事件を弁護士が解説
1.SNSグループでの“画像提供”による逮捕事件が報道に
報道によると、学校の講師の男性が、児童を対象にした盗撮画像をSNSのグループ内で共有したとして、性的姿態撮影処罰法違反(性的影像記録提供)の容疑で逮捕されました。
報道では、盗撮された児童の数は最大で100人規模に上る可能性があり、現在も捜査が続いているとのことです。
捜査機関はこのグループに共有された画像の内容や、その画像の撮影方法・対象者の特定を進めているとのことです。
今回は、こうした事案をもとに、性的姿態撮影処罰法の「提供行為」に関する規制を中心に解説します。
2.「性的姿態等撮影罪」の“提供”とはどういう犯罪か
本件で適用されているのは、2023年に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です(略称:性的姿態撮影処罰法)。
この法律では、盗撮行為自体を処罰することはもちろん、撮影された画像や映像を他人に提供・共有する行為も処罰対象としています。
具体的には、同法第3条1項、2項において、以下のような行為が「提供」として処罰されます。
• 撮影した画像や映像を他人に渡す行為
• データをSNS・チャットアプリなどを通じて共有・送信する行為
• クラウドやUSB等に保存したうえ他人が閲覧できるようにする行為
つまり、被疑者が自分で撮影していない画像であっても、盗撮された画像をSNSグループに投稿する行為が「提供」として処罰される可能性があります。
(なお、画像の児童が衣服を付けていない場合、児童ポルノ禁止法違反の提供罪として処分される可能性があります。)
3.“提供”だけでなく「撮影行為」自体も処罰対象に
現在は「提供」の容疑で逮捕されていますが、報道によれば画像のほとんどが被疑者本人によって撮影されたものとみられており、今後、撮影行為そのものについても立件・処罰される可能性があります。
同法では、提供罪と撮影罪はそれぞれ独立して処罰される構造になっており、両方で起訴されれば、その分だけ刑事責任が重くなることもあります。
また、画像の点数が多く、かつ被害者が多数存在する場合には、「反復的・組織的」な提供として、悪質性が高く評価される可能性があるでしょう。
4.複数被害者による捜査と身体拘束のリスク
本件では最大100人規模の児童が盗撮被害を受けた可能性があるとされていますが、刑事捜査においては、被害者として特定された方に対して個別に事情聴取や被害届の取得が行われます。刑事責任の判断や示談交渉も、基本的にはこの特定された被害者を対象に進められることが多いです。
ただし、被害者の人数が多く、被写体ごとの特定や保護者との連絡に時間を要するため、捜査期間は長期化しやすく、身体拘束が長く続くリスクがあります。
仮に余罪が次々に立件されれば、保釈が認められにくい、もしくは再逮捕される可能性もあるでしょう。
5.提供罪における量刑と公判請求の可能性
「提供」罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています(同法3条1項)。
不特定または多数人に提供すると、同条2項で処罰されることになり、刑が加重されます(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。
法定刑だけを見ると、初犯であれば罰金止まりで済みそうな規定ではありますが、提供行為が繰り返されている場合や、共有された画像の点数が多い場合は、当然罪が重くなりますので、正式裁判(公判請求)となる可能性も十分あります。
特に本件のように、
• 教育現場での行為であること
• 被害者が児童であること
• 画像が共有グループ内で流通していたこと
といった要素が重なると、裁判所も社会的責任を重く見て、実刑判決を選択するリスクが高まります。
6.弁護活動の視点:示談と再発防止の取り組み
このような事件での弁護活動では、被害者側との示談交渉が中心となります。ただし、示談ができるのは、あくまで「被害者として特定された方」とのみであり、「画像に写っている可能性があるが特定できない」人との示談は原則として行えません。
そのため、被害者の特定が進んだ段階で、弁護士を通じて丁寧な謝罪と謝料の提示を行い、可能な限り被害感情が和らぐよう努めることが必要です。
そのうえで、被害者不特定事案については、適宜贖罪寄付なども検討し、不起訴、罰金刑や執行猶予付判決に処分がとどまることを目標とします。
また、再発防止策として、専門機関でのカウンセリングや治療、スマートフォン等の使用制限、再就職先での指導監督体制の整備などを提示することも、処分軽減に向けた要素となります。
7.自分の行為が提供にあたるか心配な方はまずはご相談下さい
捜査が始まった段階で適切な対応を取らなければ、身体拘束が長引いたり、望ましくない形で報道が拡散してしまったりする危険もあります。
「提供行為」だけであっても、法律上は重大な処罰対象であり、取調べ対応・証拠保全・示談交渉などには、専門的な知識と経験が必要です。
当事務所では、こうした事件の刑事弁護を数多く手がけており、初動対応から示談の調整、法廷での弁護活動まで一貫して対応しております。
まずは一人で抱え込まず、ご相談ください。